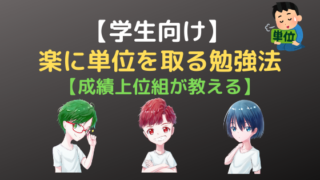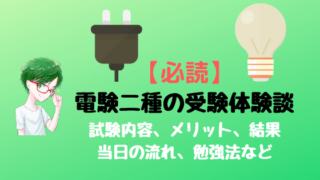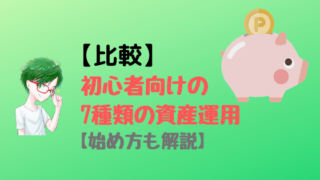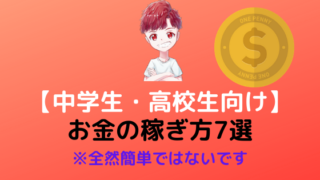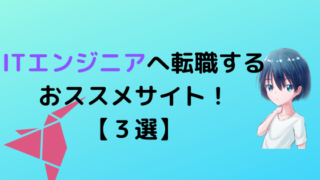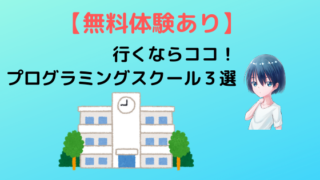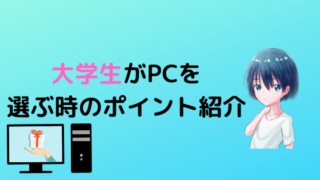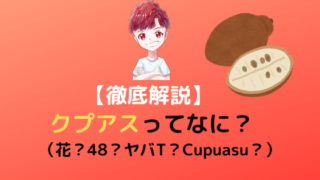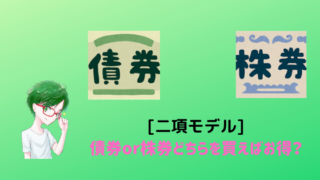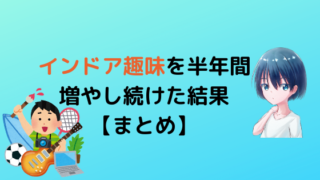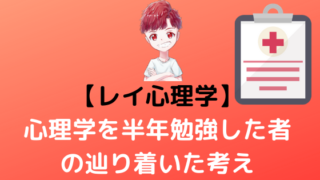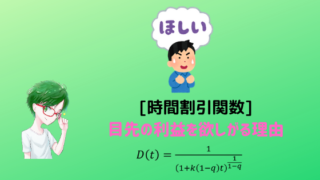こんにちは、レイです。
今回は認知バイアスの一つである認知的不協和について見ていきましょう。
ちょっと難しそうな名前ですが、なんてことはありませんよ。
認知的不協和とは
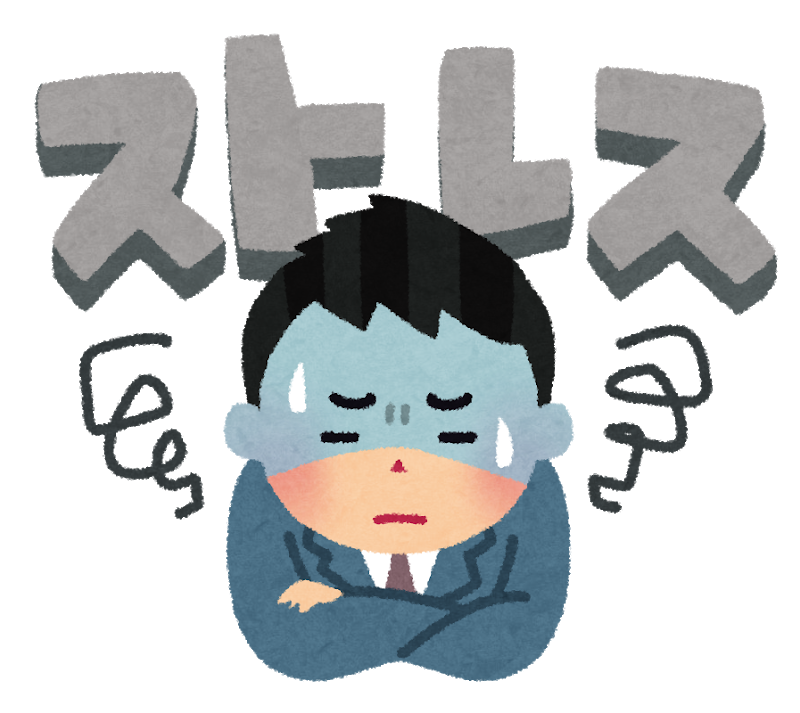
名前だけ見れば、すごく害悪なものに感じるかもしれませんが、みなさんは毎日体験しています。
元から持っている認知と相反するような矛盾したものを認知したときに覚える不快感のこと。
私の言葉で言い換えると
日常で感じる、矛盾したストレス
のことです。生きているうえで必ず体験すると思います。
認知的不協和の例
遅刻したくないけど、朝起きたくない
あの本買ったけど、こっち買えばよかったかな

認知的不協和の解決方法
大きく分けて2つ
周りのせいのにする方法と、自分の考えや行動を変える方法です。
認知的不協和の話の中で有名な「キツネと酸っぱい葡萄」という話があります。
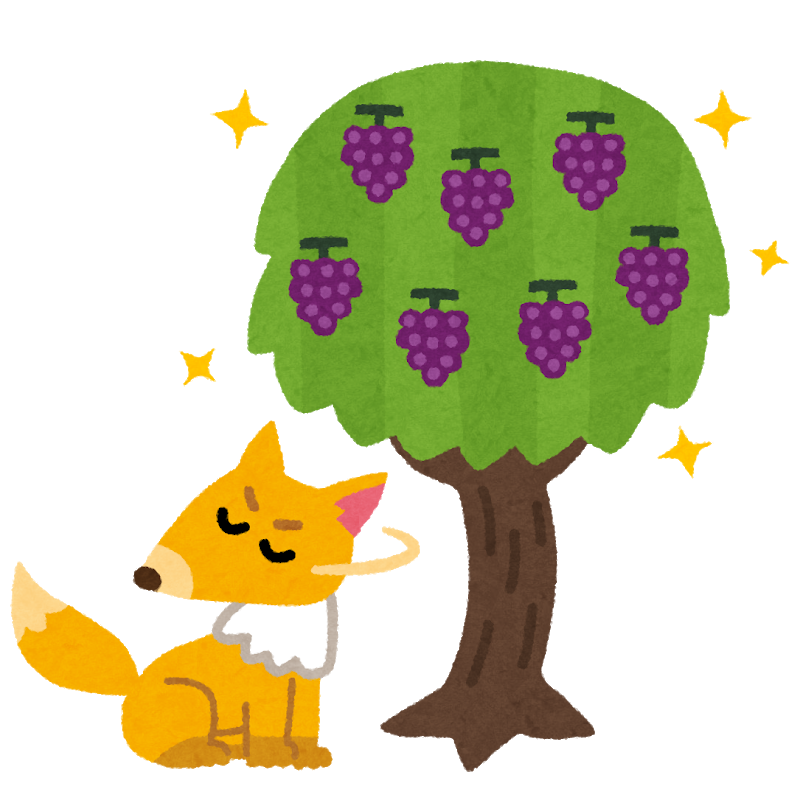
お腹を空かせたキツネは美味しそうな葡萄の木を見つけましたが、高くて届きません。
どうしても手に入れることのできない葡萄を「どうせこんな葡萄は酸っぱくて美味しくないに違いない」と言って去っていった。
という話です。自分の欲しいものであるのにもかかわらず、手に入らないとなれば、「価値のないもの」と判断し、納得させました。
欲しいけど届かないという認知的不協和を、美味しくないという事実を加えて、解決しました。
このように自分に都合のいい解釈をして、認知的不協和を解消しようとします。
これは解決方法の周りのせいにするが当てはまりますね。
勉強での認知的不協和
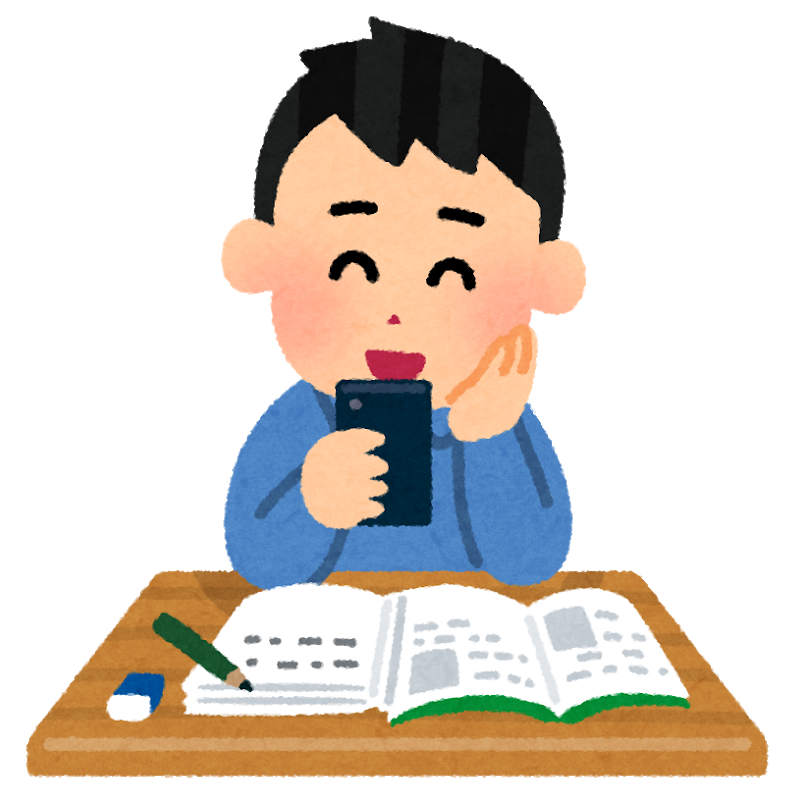
「勉強しなきゃいけないのはわかってるけど、でも勉強したくない」
あるあるすぎますよね(笑)。
これも認知的不協和の一つで、しなければいい大学には入れないという認知と、やりたくないという矛盾した認知です。(認知、認知うるさくてごめんね)
この場合の解決方法として
自分の行動や考え方を変える方法があります。
行動を変えるとしては、勉強をして勉強しなきゃいけないを解決しています。
また、考え方を変えるとしては、勉強しなくても成功する人はいるからしなくてもいいやみたいな感じです。
私は、頭が痛くて勉強できないことにしてましたね。これも行動の正当化となります。
どんな行動を取って、認知的不協和を解決するかが大事です。
葡萄の例を見て、キツネは考え方がまだまだ子どもだといえるでしょうか?
私は変えられないことを、自分の都合のよく解釈した大人な思考だと思います。
勉強の例を取れば、多くの人は勉強すべきだと答えると思います。
ただ、ある意味では勉強が意味がないということも間違いではないとも言えます。
おそらくあなたはどんな考えをして、その認知的不協和を解決するべきかなんとなくはわかっていると思います。
他人が不快感を感じたり、自分が損をするような判断をすべきではないですし、まして何かのせいにして正当化することは成長に繋がらないことも知っています。
あなたのこれまでの経験がその答えになることだと思います。
[affi id=16]
まとめ
・認知的不協和は自分に都合が悪い問題があるということ
・認知的不協和の解決には前向きなものと後ろ向きなスタンスのものがある
・確証バイアスは反証となる証拠を無視し、探す努力を怠ること
・認知的不協和の解決方法はあなたが知っている。
最後に

認知的不協和という難しい言葉で説明しましたが、要するに自分に都合の悪いことが起こったときにどう対処するかという単純な話です。
認知的不協和には、ほぼ毎日ぶち当たるでしょう。
- 会社を辞めたいけど、給料がなくなってしまう
- 眠りたいけど、眠ることが出来ない
- 彼女が欲しいけど、女の子と話すのが苦手
- 新しい自分になりたいけど、現状を変えるのは不安
などです。
全ての行動に認知的不協和はつきものです。
自分に都合のいいことばかり考えて、自分を変える努力をしないということが最善ではないことを私が言うまでもなく、あなたは知っています。
また、変えられないことを嘆いても、仕方がないときもあり、うまく自分に都合よく解釈することも大事でしょう。
最後までお疲れさまでした。